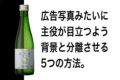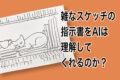カエルが最近やっている、「伝わる写真とは何か」を言語化する記事も3本目になりました。
「光の当て方」、「被写体と背景の分離」と来て、今日はシーン全体のトーンやスタイルについて言語化してみたいと思います。
皆さんの中にはトンマナ(Tone & Manner)という言葉を聞いたことがある人がいると思います。
割と最近使われるようになった言葉だと思いますが、デザイン上でのグラフィックのルールや世界観を統一するという意味のようです。
写真でも同じことが言えて、1枚の写真を仕上げるのにも、写真全体の世界観やルールを決めておくと、見る人が写真の意図を理解しやすくなりますよ。という話題ですね。
難しい話ではありません。テーブルフォトを参考にビジュアルトーンを3つの要素に分けてみました。
今回は身近で簡単に試せるテーブルフォトを題材にして、写真のトーンを深堀りしていきます。
画の世界観を決める要素として3つのポイントを選んでみました。
これは人物撮影や大きなシーン撮影でも、基本は変わらないので、応用の効く考え方だと思います。
●小道具の世界観、トーンをそろえる。
●色彩のトーンをそろえる。
●情緒的(構図的)なトーンをそろえる。

先に「和風の明るい食卓」のような写真全体の世界観やゴールを決めておくと、うまくいきやすい。
箇条書きにすると小難しく感じるかも知れませんが、意外と日常生活でも無意識のうちにやっているようなことです。実際に撮影したり、撮影プランを練っているうちに、大事なことが抜けてしまったりすることがあります。簡単なチェックリストを頭の中に入れておくと安心ですね。
小道具の世界観・トーンをそろえる。


今回初めてGeminiにサンプル画像を作ってもらいました。実写と混同しないようにキャプションを入れることにします。
テーブルフォトの要素として、小道具の役割は大きいですよね。
絵柄をわかりやすくするには、国籍、文化、季節感、性別…などのトーンを揃えておくことが大事です。
アールヌーボーやポストモダン、ゴシック調みたいなアート系の様式もこれに含まれますね。
例えば「明るい和風モダンの食卓」をゴールに日本酒のボトルを主役にしてテーブルフォトのセットを組むとしましょう。
よくある設定としてはマットな木肌のテーブルに冷酒用の小ぶりなグラス、料理はお刺身や天ぷらで、あまり華美でないトーンの土っぽい色の器に盛られている。
背景の壁のあたりには日本画が掛けられていたり、南天の実をあしらった生花がボケて写っている。みたいな感じでしょうか。
日本酒の代わりにラム酒が主役のテーブルフォトになれば小道具が日本酒のときと一緒というわけには行きませんよね。
要するにそういうことです。一つ一つの小道具が画面の世界観を支える「記号」のような役割になっていると思うとわかりやすいかも知れません。
もちろん日本酒が主役でフランス料理が脇役みたいなシーンもありえますが、基本の和のトーンまたは洋風のトーンは押さえておいて、そこから外していったほうが、うまくいきやすいと思います。
趣味性の高い小物を使うときは注意しよう。
若い頃に先輩から聞いた話ですが、ある高級腕時計の広告で、その時計が持つ「知的な世界観」を表現するために、背景に美しいアンティークの天体望遠鏡を置いたそうです。
誰もが良いアイデアだと思ったのですが、CMが公開された後、ある視聴者から「あの望遠鏡は、安ものですね。貴社は細部へのこだわりがないメーカーなのだと、がっかりしました」という手厳しい電話がかかってきました。
その後そのCMの望遠鏡部分はカットされ再編集されたそうです。
このように、趣味性の高い、車、バイク、楽器、時計、カメラ、骨董品などを小道具に使う場合はハマれば効果絶大ですが、思わぬ批判や指摘を受ける場合があるので、特に注意しましょう。
SNSが普及してからは、こういったトラブルはさらに増加傾向にある気がします。
色彩のトーンをそろえる。


清涼感を出すために、画面全体のトーンを寒色系に変えてもらいました。
色彩のトーンに関しては、2つの考え方があると思います。一つは画面全体のカラーグレーディング的な統一感。
もう一つは特定の国や文化などの色の組み合わせや特有の色彩です。
画面全体のトーンについては、クールなイメージにしたければ寒色系。温かみを強調する場合は暖色系といったシンプルな考え方でいいと思います。
時々耳にするティールアンドオレンジなどは、光と影の色温度の差を若干広げて、暖色に振ったような調整です。
他にはレトロ調だと彩度を抜いたり、セピア調にするとかなどでしょう。現実との切り分けのためグリーンやマゼンタ系に振るなどもありますね。
少し難易度が高いのは国や文化による色使いの違いです。
例えば中華風にしたいときは中国の国旗のような濃度が高くややイエローが入った赤を使うという感じです。
逆にフランスの国旗の赤は明度がやや高く青みがかかった赤でしょう。
その他南国の植物は濃度感のあるグリーン、北国の植物は彩度、明度の高い軽やかなグリーンのはずです。
これらの色に対する一般的な共通認識は意外と画の雰囲気を左右する要素になりえます。
情緒的(構図的)なトーンをそろえる。


カメラアングルを変えて動きを出したかったのですが、カエルのプロンプトがイマイチだったかも知れませんね。
最後の要素、情緒的なトーンは受け取り方に個人差があるので、若干説明しにくい部分です。
構図的な切り口でいうと、シンメトリー、三角構図などは静寂、荘厳、安定、調和みたいな感じ。
対角線や放射状の構図は、スピード感や動き。
セオリーをはずずと違和感や不安定さを感じさせる構図になると言った感じです。
写真中級者が避けたがる日の丸構図なども広告写真では消費者の視点を釘付けにする、強力で主張の強い構図として頻繁に使われています。
どの構図が良い悪いではなく、適切な場面で使い分けることが大事だと思います。
構図以外では、キャラクター小物や人物の表情であったり、喜怒哀楽といったビジュアル面で感情をコントロールするトーンは他にも色々存在します。
これらの要素が絡み合って、1枚の写真のトーンが形作られている
カエルが考える一枚の写真の世界観を決める3つの要素を言語化してみました。
これらの要素はそれぞれ独立して使われるのではなく、複雑に絡み合って写真の雰囲気を形作るものだと思います。
撮影してみて、何となく、キマらないなとか、洗練された雰囲気が欲しいなと感じたら、この3つの要素を思い出して、チェックしてみるといいかも知れません。
まとめ
これまで3回に渡って「伝わる写真ってなんだろう」という理由をさがす実験記事を作ってみました。
カエルが意識的にやっていること、無意識にやっていることが言葉という形になってなかなか面白い言語化実験でした。
これで何か引っかかるけど、それが何なのかもわからないみたいな悩みが減るといいんですが。皆さんにも似たような経験があると思います。少しでも参考になればうれしいです。
前回記事も含め、この3つの要素を意識すると、自然とアートディレクターや監督的な視点が芽生えると思います。
今回解説画像を生成AIで作ってみましたが、的確なプロンプト作成にも役立つ考え方だと確信しました。
生成AI画像をうまく使いこなしている人は、言語化することで無意識に映画の撮影監督のような思考回路になっているはずです。