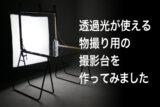今日は先日記事をアップした、自作の透過光撮影台を使っていろんなグラス(ドリンク)を撮ってみることにします。透明のアクリル板を使えば、白背景で切り抜きしたような写真が撮れる予定なんですが、こればっかりはやってみないとわかりません。セッティングを工夫してどこまでできるか頑張ってみます。
今回はモノブロックストロボを使用します。

いつもはLEDライトで記事をアップしていますが、今回はエリンクロームの100Wのモノブロックストロボ、D-Lite RX Oneを使用します。というのも、今日はビールや炭酸などの泡の出るものも撮る予定でいるからです。
LEDライトだと絞って撮影したときにシャッタースピードが長くなる可能性大です。泡のような動きのあるものはブレる心配があります。その点ストロボだと動きのある物も、しっかりと止まってくれるので安心です。
ドリンク撮影用にライトのセッティングをする


シーリングライトが盛大に映り込んでテカってます。トップライトには要注意ということでしょう。
前回、撮影台を組み上げたとき、コンデジで試しにミネラルウォーターのペットボトルを撮ってみました。その時はバックライトにソフトボックスを使ったのですが、白背景に見事にソフトボックスの布のシワが写っていました。
今回は背景のシワ防止のためにストロボの前に乳白のアクリル板を置くことにします。これで多分なめらかな白背景ができるはずです。仕上がりの理想としてはグラスだけが宙に浮いたように切り抜いたような感じで、撮れていればベストです。


ストロボの前の白いのは乳白のアクリル板。これでディフューズします。


ちなみに前回、試しに撮ったのがこれです(再登場)。ライトの出力を上げればたぶんムラは消えますが、これでは明るさの微調整ができません。
なんとなく気になっていたビールから撮ってみた
背景の自然な感じは良好、切り抜いたような描写


まずは空のグラスでテスト。バックからのストロボ1発で上から下まで、よどみなく光が回っています。
今回も、ストックフォトにアップする写真を想定して撮影しています。撮影のセッティングは以前白バックでワインボトルを撮ったときとほぼ同じです。ワインボトルのときはボトルの下にステンレス板を敷きましたが、今回はグラスのハイライトが下までくっきり入っていなくても見た目にはほぼ影響がないので、使いませんでした。
透明アクリルの天板は予想通り背景の透過光をほぼそのまま通してくれているようでグラス底の部分が暗く落ちるような様子がありません。透明の板でなく乳白アクリル板を天板として使っていたらアールのついた所から下の部分がもう少し暗くなっていると思います。
ビールのカットを撮ってみた


ビールを1人で撮るのは大変でした。泡が減っていく、ビールの量が多すぎるー等など…(;_;)
グラスの下部分のビールの色がイマイチ出なかったのが残念。泡も若干暗い、見栄え良く仕上げるためには補正や加工が必要だと思います。広告写真で見るビールのカットは、なんとも美味しそうですが、たぶんライティング、画像処理など、いろんなノウハウが隠されているんでしょう。
実はちょっと失敗カットを撮ってしまいました。

最初に撮ったカットです。透過光で撮っているんだからなんとなく大丈夫かなと気を抜いてました。正面からのライトをハニカムグリッド付き、ディフューザー越しのストロボ一発で撮ったら、泡の部分の右側がどす黒くなってました。肉眼では泡は白く見えるのですが、背景からのライトを透過しないんですね。
ライトの位置や当て方、レフのあり無しで見栄えが変わる良い(悪い)例だと思いアップしてみました。最終的には、ライトの位置を正面気味に変更してグリッドを取って、白レフを入れることでなんとか見られるカットになりました。

ビールのカット、難しいですね。撮影方法や後処理など他にもいろいろ工夫をしないとシズル感は、なかなか出ないと思います。
同じセッティングで、いろんな種類のドリンクを撮ってみた
白ワイン


白ワインは割と素直なモチーフでした。透過光の調整がうまく行っていれば、ほぼ見れる画になります。
数種類のドリンクカットを量産しようと思っていたのですが上のビールの失敗と同じく、それぞれのドリンクには、そのカットに適した光量のバランスがあって、入れ替えてパシャパシャ撮っていくというわけには行きませんでした。
考えてみれば当たり前なんですが、グラスの中身も透明なものと光をあまり通さない物があるので、考え無しに撮ると毎回ライトのセッティングを変える羽目になります。大まかに透明グループと不透明グループに分けると、多少撮影はラクになるかもしれません。
一番最初に撮ったビールなどは泡の不透明な部分と液体の透明部分が混在しているので別撮りで合成して逃げるとか、ライトやレフで調節するなど、またはビールそのものに若干手を入れるとか、ほかの飲み物より、かなり工夫が必要みたいです。たぶん今回撮った中ではダントツに難しいと思いました。
赤ワイン

赤ワインは白ワインと違ってちょっとやっかいでした。写真のワインはカベルネ・ソーヴィニヨンですが、どちらかというと光を通しにくい方の液体のようで、赤みを感じやすいのはフチや底の薄い部分あたりです。鮮やかな色味を出したければ、透明度の高い赤ワインを選ぶなどの工夫が必要だと思いました。
ちなみに、ネットで調べてみたら、高級な赤ワインほど透明感があるらしいです。撮影用だし…カエルにはちょっと手が出ませんな。
炭酸水(炭酸割り)

炭酸水・炭酸割りは今回の透明アクリル板と相性がいい印象でした。というのも回りに白いものがないほうが泡の粒がはっきりと出やすいと思われるからです。
ただ、あまり黒っぽくしすぎると軽快感が無くなりそうなので、若干他の飲み物より明るめに撮ったほうがいいのかもしれません。


冷たいものを使うとすぐ曇ってきます。でもこんな画もリアリティがあっていいかも。
アイスコーヒー

市販のペットボトルのアイスコーヒーを使ったんですがこちらも光を通しにくく、氷がよく見えなかったので少し水を加えて薄めました。さらにバックライトもやや光量を上げました。


この混ざり方、リアルと言えばリアルですが、美しくないです。
よくあるプラのプチカップに入ったミルクを入れてみたら、残念な結果に…。ミルクが一気に底の方に沈んで行きます。多分ミルクの比重がコーヒーより重いためだと思います。コーヒーにガムシロップを大量に加えたらゆっくり混ざるかもしれません。今回はガムシロップが手元に無かったので、確かめることはできませんでした。
他にもいろいろ撮ったんですが
他にも青汁、ウーロン茶などいろいろ撮ってみたんですが、これくらいにしておきます。撮ってみて、わかったのはドリンクにもいろいろ特徴があって、かんたんには行かないということ。
今回は実際の飲み物を使っているから、かわいいもんです(氷はアクリルのフェイクアイスを使用)。シズル感のあるカットを撮るときは、色んな意味で口にできないものを使うこともあります。演出だと思って見栄え優先でいろいろ試すのがいいと思います。
もう一つ撮影の順番についてですが、今回カエルはちょっと難しそうで気になっていたビールから撮り始めましたが、できればウーロン茶みたいな、比較的かんたんそうなカットから撮り始めて、撮影のリズムをつかんだほうがいいかもしれないです。
まとめ
今回は、自作の撮影台でいろいろなグラスを撮影してみました。透明アクリル板を使った撮影台は透過光の調節が割と簡単で、使いやすい印象でした。ガラス天板と異なり、アールをつけて立ち上げているので今回のような高さのある被写体の撮影もこなすことができます。
一方で液体をこぼしたとき、材質のせいなのか拭き取りにくく、かなり神経を使うこともわかりました。一番気になるのは乳白のアクリル板とどう違うのかというところですが、白背景でも天板自体が発光しているわけでは無いので、気持ちシャープに撮れる印象です。ただ乳白のアクリル板や透過性のある背景用シートも撮影現場でよく使われる定評のある背景素材なので、思ったほど大きい差が出る感じではありませんでした。今回のような飲み物ではなく、以前撮影した、オレンジとか、たまごなどは白い映り込みや、立体感などでかなり違いが出てくるかもしれません。
また透明な天板だと背景を白だけではなく自由な色に変えられるのも大きいメリットなので、機会を作ってそのあたりも試してみようと思います。それにしても、ビール飲みたかった…。塩まで入れちゃったからね。